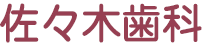「ロンドンに来れば、日本人ならたいていの人が夏目漱石を思いだしてしまう。
その感情には、一滴の血がまじるように、悲しみがまじっている。明治の悲しみ
というべきものである。」(司馬遼太郎著『愛蘭土紀行 Ⅰ』より)
既に、司馬さんが書いていた。遅まきながら最近私はそれに気づいた。
漱石を知ろうと、独学者が気ままな散策をしているとあれこれ寄り道ばかりになる。
ようやくヒントになる言葉に辿りつけたようだ。
怒りに似た悲しみを漱石が体現している。この時代、この社会に生まれ落ちた人間として
どう生きればいいのか。
濃霧が立ち込め霧雨が降りしきる夜のロンドンに、一人ぼっちの33歳の漱石を立たせてみようと
思っている。