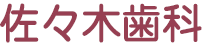1900年(明治33年)夏目漱石はロンドン留学をしている。大学の授業を早々にやめ、漱石は下宿先からクレイグ先生の家に通い個人授業を受けている。
先生の家はベーカー街にあった。シャーロック・ホームズの探偵事務所と同じ場所だ。1903年にホームズは探偵業を引退し田舎へ転居する設定になっているから、(その後も活躍はするのだが)漱石のロンドン留学中には、ベーカー街221Bに住んでいたことになる。
漱石がコナン・ドイルの探偵小説を読んでいたかは別として、漱石とホームズをロンドンで共演させる発想があったとしても何の不思議もない。何人かの作家が試みている。私もそのストーリーを考えてみよう。
「なんでも、ヨーク公のご祐筆の妹のお嫁に行った先のおっかさんの甥の娘なんだって、キャンべラ夫人は」
「へーえ。で、つまるところ、ヨーク公のなんになるんで?」
「だからさ、ご祐筆の妹のお嫁に行った先の・・・もう、さっき言ったでしょう、おっかさんの甥の娘だって」
「はいはい。う~ん、分かったことにしましよう。話が前に進みませんから。」
「そのキャンベラ夫人が可愛がっていた猫がいてね。」
「ほう、ペルシャ猫かい?」
「いいや」
「シャム猫かい?」
「いいや」
「化け猫と言ったら、はったおすよ。ロシアンブルーかい?」
「いや、日本のミケネコ。日本びいきで、なんでも、日英同盟を祝って日本のミケネコを飼うようになったらしい。
そのミケが失踪したのさ。」
「貴族の生活がネコなりに退屈だっんじゃないかい?毎日ローストビーフ喰ってたらたまにはアジの干物が恋しくなるわな。」
「事件は、ネコがダイヤの首輪とともに行方不明になったことだ。ビクトリア女王の形見分けで、左側のイャリングのダイヤを使った由緒ある宝石らしい。」
「へ~え。さぞかし首輪が重くてミケは猫背になったろうよ。かわいそうに。」
(つづく)